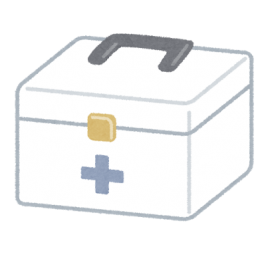面倒な確定申告の支払調書、青色申告決算書の作成も終わって、いよいよ申告書本体に取り掛かる段階に!
「これは、俺とヨメの二人がそれぞれ作りゃいんだよな?」
「そうよ、アタシは源泉徴収票をつけて、それから、国民年金の支払証明書をつけて・・・っと。」
「オイ、ちょっと待て、この生命保険と共済は、俺とお前のどっちに使うんだ?両方あるぞ?」
「え?国民健康保険はアンタの名前なんだから、そっちでしょ?」
「なんでだよ?お前の口座から引き落としてるじゃないか?」
「じゃあ、医療費控除ってのはどーすんのよ!?アタシの名前だから、アタシのほうから引くの!?」
「なんでだよ!払ったのは俺だろ!?」
さてさて、困りましたね。「払ったのは夫なのに、領収証名義は妻」こういうものって結構多いですよね。鳶の親方とヨメ鳶、どちらから引くのがいいのかを確認していきましょう。
法律のルールは「払った人」がキホン・・・だけど?
鳶の一人親方のような個人事業主で、妻と小さな子だけの家庭の場合、控除で登場する主なものを挙げてみましょう。
・社会保険控除(国保、年金など)
・生命保険控除(生命保険、こくみん共済などの保険)
・寄付控除(ふるさと納税など)
・医療費控除(病院等で目安としては年額10万を超えたとき)
このほかに小規模共済掛金、雑損控除などが登場する場合も考えられます。一般的には上のようなものが理解できていればOKでしょう。
さて、これらの「控除=収入から差し引いて良いお金」は親方鳶職人と、奥さんのどちらから引けば正解なのでしょう?
法律上のルールでは、「払った人から引いて良い」というルールになっています。出産費用などの医療費は領収証が奥さんでも、実際の支払は夫である親方鳶職人の収入から出ているので、ご主人の収入から差し引くことができます。
個人事業主はヨメ鳶の給料から差し引いても問題ナシ
ところが、個人事業主の場合、事実上は「どちらから引いても正解」になります。なぜなら、専従者の給料は、夫である親方鳶職人の稼ぎから払われているから。
つまり、もともと、親方の財布から出て、ヨメ鳶にわたっているお金なので、どちらから引いても問題はない、ということになるんですね。
節税効果の点でいえば、控除は一人に集中させるのが効率がいいといわれます。ヨメ鳶の稼ぎが小さい場合は、保険料も、医療費控除も親方から差し引くのがキホンと思っていいでしょう。
親方もヨメもそこそこ稼ぎがいいと、保険や医療費などは、ヨメ鳶から引いたほうがメリット大になるケースも考えられます。そのへんは、実際の収入額に応じてシュミレーションが重要!実際の金額でシュミレーションしてみるといいでしょう。
友達にも鳶の事を教える。