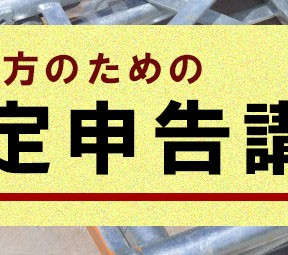鳶が足場を組み上げるまで!
鳶が足場を組む作業工程を関係者以外が完成まで追うことは難しい 鳶に興味がある人のために、足場設置の流れを解説しよう! 建設現場において、当たり前のように組み上がっている足場。クサビ式足場は(1)作業前の工程、(2)第1層目の組立工程、(3)第2層目以降の組立工程、と大きく3つの工程で組み上げられる。 ■作業前の工程 足場作業に入る前にまず決めないといけないのが作業主任者、いわゆる“職長”だ。職長は技能講習修了者の中から指名され、作業現場の組立図や写真、また実際に現場へ行き敷地や地盤、障害物があるか、建物の特徴などを確認。そのうえで足場を組む鳶の手配を行い作業の分担を決める。 また現場の状況を考えながら必要な足場部材の手配が必要となる。部材が現場で足りなくなることが問題になるのはもちろん、多すぎても撤収作業などに時間がかかってしまうため見極めが重要な作業だ。 ■第1層目の組立工程 トラックより部材を降ろした後、最初の作業となるのが建物周辺に手摺(水平材)を配置することだ。その後、ジャッキの下に敷く敷板“ジャッキベース”をアンダーベースの上に固定。支柱を支える脚部の固定作業を行ったあと、建物のコーナー部に設置したジャッキベースから支柱を差し込んでいく。支柱と支柱を手摺を使用しハンマーで打ち込み固定。手摺を内側の支柱に固定し、建物に応じたスパン(間隔)を決めながら連結していき、作業床の取り付け位置が決め踏板をはめ込んでいく。 ■第2層目以降の組立工程 まずは第1層目と同じく建物のコーナー部から支柱、手摺を中央に向けて固定していき支柱の建込みを進めていく。次に手摺、ブラケット(アンチをはめる資材)、踏板を取り付けていき3層目以降は同じ工程を繰り返す。 ブラケットや足場板など部材は渡す側と受け取る側それぞれが分担作業とし、主に親方が組み立て作業を行っていくのが一般的だ。 ※上記はあくまで一般的な組上工程で、それぞれが並行して進むケースもあります。