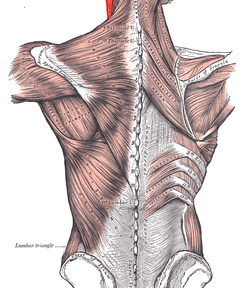支柱【知って得する! 鳶用語辞典】
【用語名】 支柱 しちゅう 【使用用途など】 こぶ(コマ、ポケットとも)という緊結部が一定間隔ごとについている鋼管。このこぶと水平材や斜材の緊結部をくさびにより緊結することで、くさび緊結式足場は組み上がっていく。 支柱には長さの異なる幾つかの種類が存在し、これらを組み合わせることでどんな高さの建物にも対応できるようになっている。 その独特の形状から運搬が難しい支柱だが、中でもサブ(サブロク)と呼ばれる種類の支柱は全長3.6mと長く、取扱いは非常に困難だ。サブの運搬、受け渡し作業は、新人鳶にとって最初の関門となるだろう。 【市場価格】 一本あたり3000~10000円(長さによって変動)