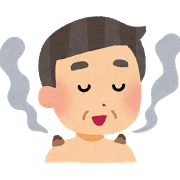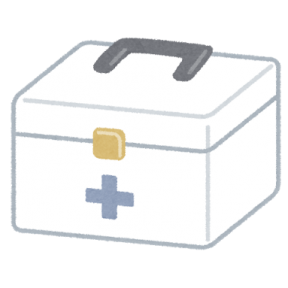建築限界【知って得する!鳶用語辞典】
【読み方】 建築限界 けんちくげんかい 【解説】 交通工学の用語のひとつ。 道路使用には建築限界という、線路・道路に対しての安全を確保するために、定められた範囲内には障害となりうる建築物等(固定・非固定にかかわらず)を設置してはならない、という概念がある。道路使用許可申請を出す際には、この建築限界の範囲を厳守するようくれぐれも注意しなければならない。 ちなみに具体的な数値としては、 ○歩車道の区別がない道路 … 幅員の1/8以下 ○歩道 … 幅員の1/3以下(有効幅員1.5m以上確保) と、各自治体で条件が多少違うことがあるものの、およそこれらが基準になってる。 例を挙げれば3mの幅の歩道があるとして、建物側から1m以下までの土地であれば足場を立ててよいことになる。 道路使用許可申請を出すときは、周辺道路や歩道の幅は必ず現調時に抑えておかなければならない。