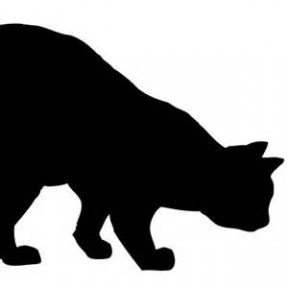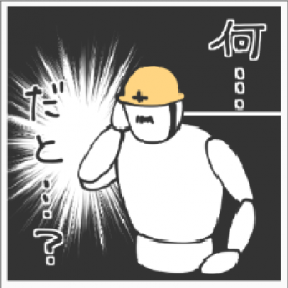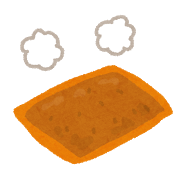春の気まぐれ強風対策!覚えておきたい作業を中止すべき天候
春先の天候は気まぐれ、なんてよく言われますよね。 春一番は去っても、三寒四温の不安定な気圧配置は、唐突な降雪や、雨、突然の突風を招くなど、本当に不安定な天気が続きます。 特に高所は遮蔽物が少ないため、風の影響を受けやすい場所。 風よけのネットやシートが突風でめくれあがったり、足場倒壊の原因になるなど、お天気は仕事の安全性にも大きな影響を与えます。 危なくなったらすぐ撤収!が鉄則になってきている近年、作業をやめるべき天候について、おさらいしておきましょう。 法律で決められている「作業を中止すべき天候」を知っておこう! 建設業は一歩間違えると過酷な労災事故が発生する危険と背中合わせの仕事と言われています。 これは、言い換えると「厳しい安全基準を守らないと、過酷事故が起こりやすい」ということです。 そこで、労働安全法施工規則では、「作業をやめるべき悪天候」を細かく定めることで、事故を未然に防ぐような仕組みづくりをしています。 ざっくりまとめると、次のようになります。 1.1時間あたり50mm以上の降雨(大雨警報が出るくらいの豪雨) 2.1時間に25cm以上の積雪(これも、大雪警報が出るくらいの豪雪) 3.10 分間の平均風速が毎秒10m以上の強風のとき(後述) 4.震度4以上の地震(中震…後述) 足場の仕事をするための資格を受けると、技能講習や特別教育などでも必ず登場する内容ですから、その意味でも覚えておいて損はないですね。 風速毎秒10mってどのくらいの風? 雨や雪と違い、風は目に見えないので「強風」の感覚がつかめないのではないでしょうか。風速毎秒10mというと、基本的には台風並みと思っておけばイメージしやすいでしょう。 実際には、周辺のモノの動きなどを参考にして、早めの危険予知をすることも大切です。風速10mクラスの風が吹いている様子の動画を見てみましょう。 こちらは風速を体験できる施設での様子。子どもさんが着ている上着が風速10mから、旗のようにバタバタとはためいています。15m毎秒になると、ほっぺたや目が風圧で押しつぶされるほど強烈な風だということがよくわかります。 震度4の地震は「立っているとよろける程度」 地震は予測のしようがないものですが、他の3つは天気予報で予測ができるものです。朝、作業に入る前、作業中もこまめにチェックしておきましょう。 震度4は、建物倒壊の恐れはありませんが、そのまま立っていると、よろける可能性は多分にあります。こちらの動画は地震体験施設のもの。震度4の目安の参考にしてみてくださいね。