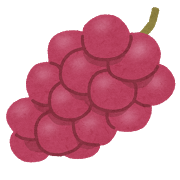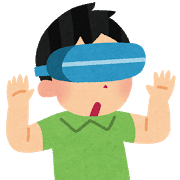足場の上で地震が来たら!?事例で知る鳶の地震対策
ここ20年ほど大規模な地震が頻発している日本列島。南海トラフ地震や、首都直下型地震など、今後も大きな地震が起こる可能性が心配されています。 もし足場の上にいる時に大きな地震に見舞われたら!? 鳶職人はどんな行動をとればいいのか?過去の事例から必要な対策をまとめます。 その時鳶はどうした東日本大震災の時の鳶職人の動き まずは実際に地震が起きた時に職人たちはどのような対応をしたのか?事例を見てみましょう 3.11 東日本大地震 千葉県北西部の建築現場にて こちらは東日本大震災発進時の建設現場にいた鳶職人の動画です。激しい揺れの中、必死で足場屋鉄骨にしがみついて振り落とされないように身を守っている様子がよくわかりますね。 地震の怖さは、 ・いつ起こるか分からない ・どの程度激しく揺れるか分からない ・どのくらい続くかわからない というところ。 住宅建築中の頑丈な足場の高所に乗っている場合なら、地震が起きた場合とにかく落下転落を避けることが第一です。無理をして飛び降りようとしたり、慌てて降りようとすることで転落を招く恐れもあります。 反対に低い場所にいて、安全帯をつけていない不安定な状態であれば、建物から離れた落下物の恐れがない場所へ非難するほうが有効です。 ■鉄塔の積み上げ作業中に地震発生!その時鳶は? 鉄骨鳶、橋梁鳶の場合は、住宅よりもはるかに高い場所で作業している最中に地震に遭う可能性もあります。高さがより高いときに地震に遭ったらどうなるのでしょうか? こちらは、鉄塔くみ上げ作業の最中に震度3の地震が来た時の様子です。震度3というと、「揺れている」とはっきり感じることができる程度で、さほど大きな地震ではないせいか、作業者のみなさん、そのまま仕事を続けておられます。鉄塔の場合は風で揺れが起こることもあり、そこに小さめの地震が来ても「強風?」くらいの印象なのかもしれません。 地上数百メートルとなれば、落ちればまず助かりません。建造物が頑丈であることを期待して、振り落とされないことを最優先するほうが良いのでしょう。 倒壊の恐れがあるときは? あまり想像したくないことですが、地震で足場が倒壊する可能性もなくはありませんね。そういう場合は、むしろ安全帯をしていることで、足場に引きずられてしまう危険があります。 自分のいる高さによって、地震の時どうするのが最も安全なのか?は、ケースバイケースで判断が難しく、一概には言えません。 倒壊の恐れがあるような状況では、巻き込まれないことで助かる確率が上がります。打撲のダメージを少しでも少なくすることも救命率を高めます。 いざという時の瞬間的な状況判断と、鳶ならではの体の柔軟性、筋力を活かして生き延びるしかありません。普段からVRなどで安全教育を受けておくことも役立つかもしれませんね。