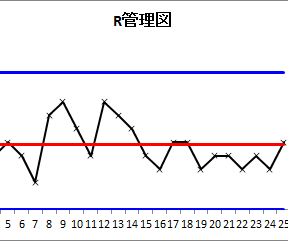知って得する!安全帯特集 第1回
安全帯、よし!・・・大きな現場の朝礼では必ずやるお決まりのフレーズですね。 高所をはじめとする危険な箇所での作業が多い鳶にとって、安全帯はいざという時に身を守るためになくてはならない存在です。 ですが一方で、現場に入ってみると安全帯を付けてはいるものの、肝心の使用法が適当になっている職人さんを多く見かけます。 気持ちはわからなくもないですが、安全対策を疎かにするというのは、自身だけでなく周囲の人間まで命の危険に晒しかねず、絶対に改めなくてはいけません。 今回はそんな安全帯についての特集記事となっています。安全帯の正しい装着方法や、どんな場所で使うよう定められているか、どんな種類があるかなど、徹底的に紹介していきます。 まだまだ足場のことを把握しきれていない新人鳶さんはもちろん、足場のことなら任せとけ!なんて胸を張って言えるようなベテラン職人さんも確認&自分への注意喚起ということでぜひご覧ください! 作業員の命を守る!安全帯の重要性とは!? まずは基礎中の基礎、安全帯とは何か?というところから触れていきましょう。用語集「安全帯」によると、こう解説されていますね。 高所から落下を防ぐ為に着用する金具付きロープ、及びそれを装着する胴ベルト(ハーネス)。文字通り高所作業を行う職人の命綱であり、安衛則においても、高さ2メートル以上の箇所での作業時にはこれを必ず使用しなければならないとされている。 大きく分けて「腰ベルトタイプ」と「ハーネスタイプ」の二種類があり(詳しくは用語集内の各ページを参照)、戸建てなど低層かつ足場のつくりが複雑な現場では腰ベルトタイプが、反対に高所作業がメインとなり、より安全性が重要視される高層の足場ではハーネスタイプが適していると言えるだろう。 (用語集「安全帯」より) これを見てもわかる通り、安全帯は基本的には作業員が誤って落下してしまわないためにある、と考えて問題ないでしょう。 墜落事故は現場作業員の死亡原因断トツの第一位。その墜落事故を防ぐための装備と考えると、安全帯がどれだけ重要なものなのか理解してもらえると思います。 ちなみに、安全帯には大きく分けて胴ベルトタイプとハ-ネスタイプの二種類が存在します。 胴ベルトタイプは付け外しが容易で、作業中も邪魔になりにくいのがメリットです。戸建てや低層のアパートの改修工事などをメインに行う職人たちはこちらのタイプを好むようです。 対してハーネスタイプの一番の利点としては、胴ベルトタイプと比べて墜落時の衝撃が全身に分散され、人体に受けるダメージが少ないことが挙げられます。(胴ベルトタイプの場合、どうしても腰部分に衝撃が集中してしまいます。) より高所での作業が多くなる高層ビル等の大型現場をメインに活躍する職人はほとんどがこちらのタイプを使用していますね。(元請けによってはハーネスタイプの使用を現場入りの必須条件にしているところもあります。) また、最近では安全帯のフックの掛替え時の墜落の危険を低減させるため、写真のように安全帯のランヤードを2本にして、どちらかのランヤードを常に足場や親綱につなげることが出来る二丁掛け安全帯が使用されているようです。(こちらも元請けによっては二丁掛けを必須としているところもあります。) さて、ここまでは安全帯がいかに重要なものであるかについてお話してきました。 続いては安全帯を使用する作業や場所について触れていきましょう。 安全帯を使用しなければならない作業としては具体的に次のようになります。 ①作業床(幅40㎝以上)がない場所での作業 ②作業床があっても墜落防護措置(手すり等及び中さん等)がない場所での作業 ③墜落防止用の防網が張られていない場所での作業。 ④手すりから身を乗り出しての作業 ⑤開口部からの資材の搬出入の作業 (建設業労働災害防止協会『足場の組み立て等工事の作業指針』より引用) これらの作業を高さ2m以上の地点で行う場合、安全帯を使用しなければならないとされています。 特に気を付けたいのは②④⑤が同時に起こる可能性がある足場材の受け渡し作業ですね。 高層の現場ともなると、上に合わせて移動して流れながら足場材を受け取り、上に渡していく、といった動きが基本になります。 …