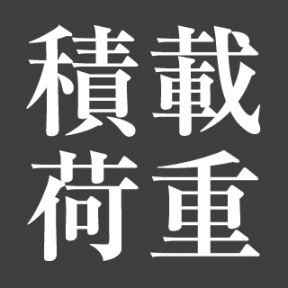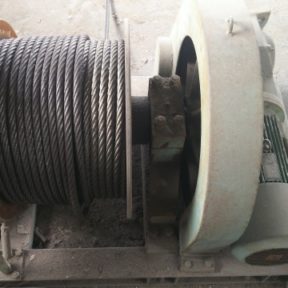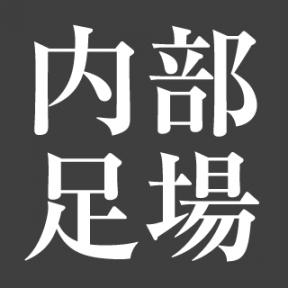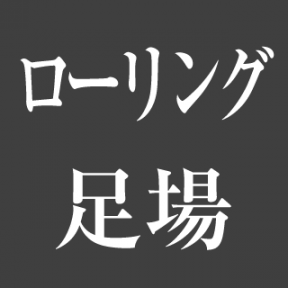イマトビ・カコトビ 第二回【松川 友和】さん
現在の仕事を始める前に鳶職人だった人、異業種から鳶の世界に入ってきて活躍している人。そんな人たちを紹介する「イマトビ・カコトビ」!今回は鳶から転身し、なんと芸能プロダクションのCEOになったカコトビさんを紹介したいと思います! 『Cocoro-toプロダクション』 CEO 松川 友和さん (会社公式サイトURL・・・http://cocoroto.tv/about_cocoro-to/) 『Cocoro-toプロダクション』 は広島で地域密着型の芸能プロダクションとして、イベント開催や、企業、イベントへの人材(タレント派遣)を行う会社です。松川さんはそのCEO、つまり代表として第一線で活躍されている方なわけです。一見鳶とはあまりにもかけ離れた世界の方に見えますが・・・。 松川さんは広島の高校卒業後、10代後半から20代前半にかけてボーイズバーの店長、エステのカウンセラー、男性用精力剤の販売など、実に多くの職業を経験したそうです。年齢に見合わない高報酬を貰えていた時もあれば、トラブルに巻き込まれ、人生のどん底と言うような喰うにも困るような時期もあり・・・と、かなり波乱万丈な日々を過ごしていたようです。 そんな多様な職業の中で、松川さんが最も有意義だったと言う仕事、それが「鳶職」なのです。彼は鳶という仕事の良かった点として、「オンオフがはっきりしている」ことを挙げています。現場の時は仕事のことだけを集中して考える。その分現場を出れば完全に自由、仕事を家に持ち込むこともなく、好きなことをし、好きなことを考えられる。このオンオフの切り替えが、松川さんに心の余裕を生み、今までの自分を見つめ直し、これからのことをじっくり考える時間を作れたようです。 積込や移動の時間も考えると鳶職は拘束時間が長め・・・なんていう人も居ますが、その分やることさえやってしまえばそれで打ち止め、デスクワークにありがちな煩わしい事務仕事や、家に持ち帰っての残業なんてものはありません。プライベートの時間を心から満喫できる、これは鳶という仕事の大きなメリットなのかもしれませんね。













-288x288.jpg)