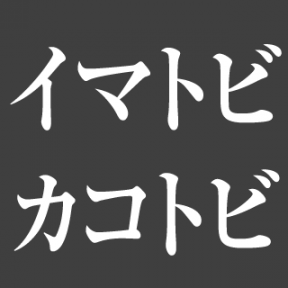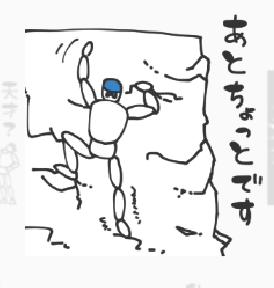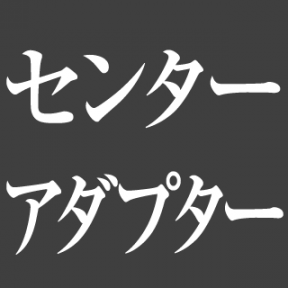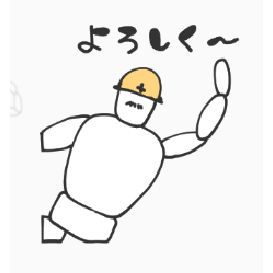現場に欠かせぬ必需品!おすすめゴム手袋特集!
ゴム手袋。それは現場道具の中で一番消耗が激しく、それでいて現場作業には欠かせないモノです。普通に使っていると3日も持たないなんてザラで、それでいてすぐ失くしてしまうので現場についたはいいものの、うっかり手袋を用意し忘れる・・・なんて経験皆さんも一度はあるのではないでしょうか?笑 そこで今回は、そんな現場の必需品ゴム手袋の中でも特に職人さんたちの人気が高く、かつコンビニなどで取り扱っていることが多く入手が簡単なおすすめゴム手袋を紹介したいと思います!それでは、さっそく行ってみましょう! 1.【ショーワグローブ】グリップ(ソフトタイプ) (出典:http://www.sanwahard.jp/?pid=15160066) まず最初に紹介したいのはこちらのゴム手袋。特徴は何といってもその丈夫さです!普通のゴム手袋は現場での作業を続けるとすぐにぼろぼろになってしまいますが、本商品に使われている厚いゴムはハードな作業にも耐えてくれます。また、ただ厚いだけでなく柔軟性もしっかり持ち合わせているので、組み立て作業に支障をきたすこともありません。コンビニでの取り扱いが多く、値段も安価なのも高ポイント。コストパフォーマンスを重視するならこれでしょう! 2.【ショーワグローブ】組み立てグリップクラスター (出典:https://www.monotaro.com/g/01013173/) 次に紹介するのが同じくショーワグローブから出ているこちらの商品。その特徴はバツグンの作業性です。前述の商品と対照的に、こちらのゴムはやや薄めで指先へのフィット感を重視した構造になっており、手先を使った細かな作業も違和感なく行えます。かといって特別に耐久性が劣るかと言えばそんなこともありません。値段こそ少し高めですが、それだけの価値はあるはずです!作業の効率を少しでも高めたいと考えるなら是非一度使ってみてはいかがでしょうか!こちらも多くのコンビニで取り扱っているので容易に手に入りますよ。 3.【富士グローブ】ラテックススペシャル 作業用手袋 10双組 BIG DRAGON (出典:http://www.koguru.jp/113_8198.html) 最後に紹介するのがこちらの商品。特筆すべき点はズバリ、とにかく安いということ!上記の通販ページでは1000円を切っており、お近くの工具店やホームセンター、ワークマンなどでも同価格帯で取り扱っているはずです。失くしやすく、壊れやすい手袋が一双あたり100円以下で手に入るのはかなりの破格と言えるでしょう。10双まとめてパック売りしているので、思い切ってパックごと鞄に入れておけばうっかり持っていき忘れることもなくなるかもしれませんね!笑 まとめ いかがでしたでしょうか?ゴム手袋なくして現場仕事は始まりません。 皆さんも今回紹介した手袋や、自分のこだわりのゴム手袋を身に着けて、明日からも現場作業頑張っていきましょう!