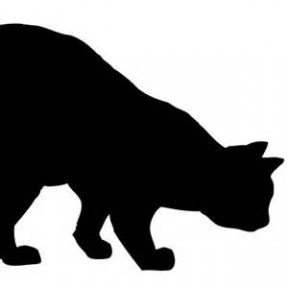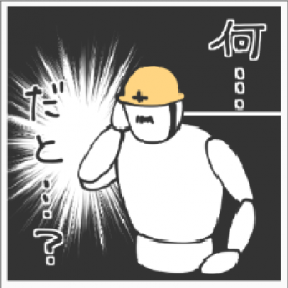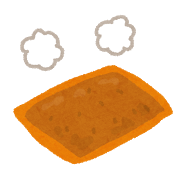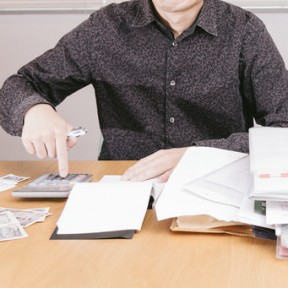成人したら変わる?知っておきたい鳶職の仕事・未成年と成人の違い
今年の成人式から早一か月、新成人の皆さんはいかがお過ごしですか? 新成人になったことで、鳶職人としても気持ちを新たに、やる気UP!な人も多いのでは? ところで、鳶職人のように高所作業をする職人では、仕事の内容が年齢で変わる場合があります。 今回は鳶職の仕事で、成人と未成年で違いがあるものをまとめてみました。 法律は意外に厳しい!?高卒鳶職人は高所作業の年齢制限アリ 鳶職人の仕事で年齢によって大きな違いがあるのは、「高所作業の制限」です。 これは労働基準法によって制限が決められていて、5m以上の高さの場所(高所)で作業は制限がされています。 18歳未満の鳶職人は、 ・5m以上の場所では作業は禁止 ・足場の組立会たち等作業は禁止(高さ制限なく禁止されています) (年少則第8条24、25号) と、意外と厳しいルールと思っておいたほうが良さそうです。 ただし、補助作業は禁止されていないので、「地走り」作業は問題なく行えます。 18歳未満、ですから18歳になれば問題はなく、高所作業も、解体もやらせてもらえるようになります。 また、18歳未満は深夜労働も禁止されているため、午後10時から午前5時までの時間帯の仕事もNG!夜の突貫工事などはダメです。 また、1日働ける時間、週間の労働時間にも制限があります。 中卒鳶職人の場合は「保護者の同意」が必要になることも! 鳶職人を目指す人の中には、中学校卒業してすぐに入門してくる人もいますね。 労働関連法では、年齢が若いほど、安全確保のために仕事の制限や条件が細かく厳しくなります。 ざっくりと並べてみました。 ・年齢確認書類を会社に提出 ・親権者からの就労の同意書 ・保証人(通常は親権者) ・残業は禁止 ・深夜勤務NG ・給料は本人に払う(親の口座入金させないこも) ・有害・危険業務やトンネル作業は禁止 ・高所作業・重量物の移動などもダメ 中卒の作業員ができるのは、地上で行う仕事だということがよくわかりますね。 親の承諾書を取っているから、といっても、高いところに登れるわけではないので気をつけておきましょう。 特別教育を受けても年齢がクリアにならないとNG! 足場の場合、年齢と無関係に特別教育を受けないと、高所作業をしてはいけないことになっています。 この特別教育そのものは、誰でも先に受けておくことはできますが、受講を済ませたからといって、作業はできません。 年齢条件を満たさないと実作業には着けないので、勘違いしないように気をつけましょう。