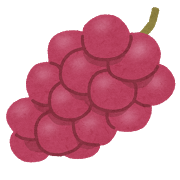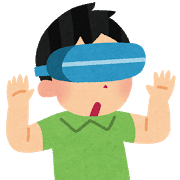増える逆上ドライバー!トラッカー必見の交通トラブルを防ぐ三原則
ニュースで頻繁に報道されている、「逆上ドライバー」による路上トラブル。 社用車で資材運搬を任されたり、通勤に車を利用する鳶職人にとっても、他人ごとでは済まされないですね。 万一の場合に備えて、逆上ドライバー対策をまとめます! 急増中!逆上ドライバーによる「路上トラブル」とは? ここ最近、急増している「逆上ドライバー」による交通トラブルが社会問題になっています。 つい先日も、今年6月に東名高速下り線で起こった、交通トラブルの犯人が逮捕されたニュースがテレビで繰り返し報道されました。 この事故では、逆上ドライバーに高速道路の追い越し車線で車を強引に止められた上、逆上ドライバーが停車させたワゴン車から、運転していた奥様と、後部座席のご主人を引きずりだそうとしていたところに、後ろから大型トラックが突っ込んだというもの。 不幸にも、ワゴン車のご夫婦は亡くなってしまい、後席の娘さんたちも大怪我を負いました。楽しい家族旅行の帰り道を、思わぬトラブルに巻き込まれて両親を失った事故のキッカケは、 「パーキングエリアで、違法駐車していたのを注意されたから。」 というとんでもなく自分勝手な理由だったそうです。しかも、犯人は、問題の事故以前にも、他県で3回も同じようなトラブルを繰り返していました。 恐ろしいことに、こうした「身勝手で自己中心的な理由で、激怒して交通トラブルを起こす」ドライバーが急増していることが指摘されています。 逆上ドライバーは「身勝手な理由」で襲ってくる!? 逆上ドライバーには共通点があります。 いくつか、最近発生した「逆上ドライバーによる路上トラブル」の事例をあげてみましょう。 ●交通トラブルで互いに「煽られた!」と口論し、ワイパーをつかんだ土木作業員を20m引きずって軽自動車が暴走(愛知県:2017年10月) ●道譲れ譲らないで歩行者をトラックでひく ●バイクの高校生に追い抜かれた時「馬鹿にされた」と感じ、車ではねたあと、何度もひいて殺害(平塚市:2016年7月) どのケースでも 「駐車場所を巡って腹が立って殴った。」 「煽られてカッとなった。」 「追い抜いた時、ガンつけられたと思った」 など、一方的な思い込みで腹を立てたまま、トラブルになっているのが特徴です。 相手の勝手な怒りをぶつけられて、死亡事故や怪我をさせられたのではたまったものではありませんね。こちらには落ち度がなくても、相手の勝手な思い込みで、いきなり逆上するのでは、いつ、トラブルになるかわかりませんし、トラブルにならない予防が必要です。 万一のときは「離れる」「開けない」「ハザード」で対処! もしも、予期せぬ出来事で逆上ドライバーに出くわしてしまったら!?そんな時の三原則は、 ①離れる 無理やり車を止められるようなら、物理的接触を避けるのが最大の予防!可能な限り、物理的に接触しないようにします。 ②開けない 相手が車の窓を開けるように要求してきても、絶対に応じないことです。車体を激しく蹴る、窓を割れそうな勢いで叩くなどの行動をされても、車は簡単には壊れません。窓とドアロックを閉じて返事をしないように口も「開けない」ようにします。 ③ハザード 周囲に異常事態を知らせるためにハザードを点灯して、危機を伝えましょう。 車の中で可能であれば、証拠のために録音、録画をする、警察へ通報するなども行えるとベターです。万が一のために、普段から冷静な対処を心がけましょう。