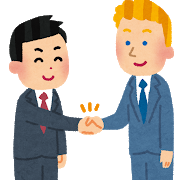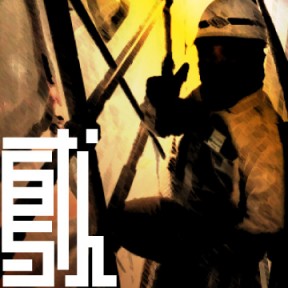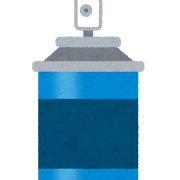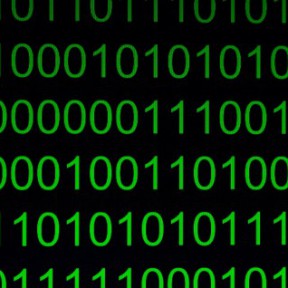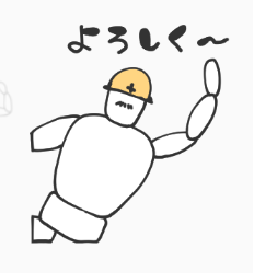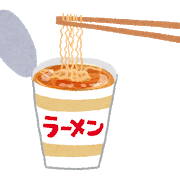【外国人雇用が変わる!】言葉の壁をぶちこわせ!現場でのコミュニケーション方法を整理する
4月から新入管法で増加が見込まれている外国人職人たち 建設業、農業で特に人手不足が深刻化している今、外国人労働者にかかる期待は嫌でも大きくなります。 建設業界では以前から外国人研修生として、職人見習いの受け入れが行われてきています。 既にアジア諸国からやってきた研修生と一緒に仕事をしている会社も多数登場しています。 さて、そんな外国人労働者がさらに増えるにあたり受け入れ側がまず、心配するのは ことばの壁 ではないでしょうか? 現場での外国人とのコミュニケーションを円滑に進めるポイントをまとめました 日本語レベルと仕事力は別の問題と認識しておく 「日本語が話せるから」という理由で、誰もが鳶職人として優秀だということではありませんね。外国人だって同じです。 日本語が流暢な奴=良い職人ではありません。 ・仕事に取り組む姿勢 ・よく理解して、やっていこうとする意欲と態度 これらをきちんと前面に押し出して、積極的に取り組むことができれば、国籍だとか、人種だとか、日本人だ、外国人だということは問題にはならないでしょう。 鳶職人の場合、応募してくるのは、現地である程度経験を積んだ人材なので、全く右も左も分からない人物ということは少ないことも考えられます。 日本人でも「減らず口」とか「舌先三寸で仕事をする」など、しゃべってばっかりで手が動かない人物は一定数いるものです。 まず「しゃべれるから仕事もできるだろう」という思い込みで見ないことも大事です。 メモができない時は音声で!現場を回しながら基本語句をマスターへ! 今回の改正で、外国人労働者には日本語力のテストなどを実施して、基本的な会話能力をある程度チェックできる仕組みは準備されているようです。ただ、テストの内容は原則日常生活に近いものが多く、実際の雇用現場ではテストで出題される以上の範囲の日本語能力が求められることが指摘されています。 現場で使う工具や部材の名称は、こまめにメモすることができるとベターですが、仕事を回しながらだと難しいものです。 オススメは休憩時間に音声や動画で録音してしまう方法。 仕事が終わってから見直し・聞き直しができるので習得が早まる期待ができます。 先輩研修生の中には、Youtubeなどを利用して日本での足場業界情報を共有してくれている人もいます。 ここで大切なポイントは、 日本にシゴトに来る外国人は、日本語の上達を希望している ということ。 つまり大切なのは「向こうがどのぐらい勉強してくるか?」ではなく、「こちらが積極的に伝えようという姿勢を見せること」だとも言えますね。