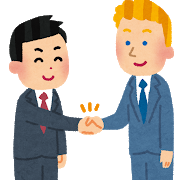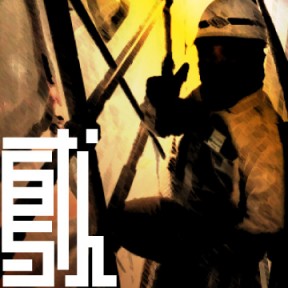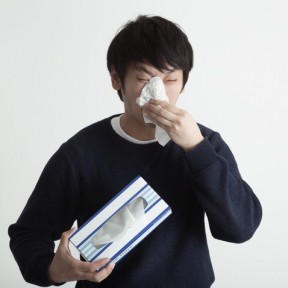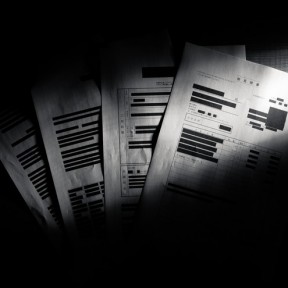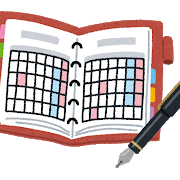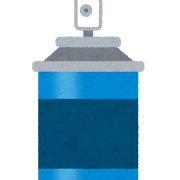全国の鳶に警鐘!飲酒運転を予防せよ!飲んでも残らないコツ
4月は新年度!花見、歓迎会シーズンですね! 春といえば桜!花見だー!で飲む。 新入社員が入ってきた!歓迎会だー!で、また飲む。 その合間にも、なんだかんだで飲み会が続くと、はっきり言って、 翌日残りませんか? 飲酒の怖さは、自覚できないまま、体にはしっかり残っていること。 飲むことそのものよりも、「残らないように飲む」と方が難しいし、大切なんですね。 歓送迎会が続くこのシーズン、お酒を翌日に残さないためのコツについてまとめました。 食べてから飲むは基本中の基本 意外と忘れられているのが「お酒を飲む前に食事をする」ことです。 食べないでお酒だけを飲むと、アルコールが急激に体に回ってしまって早く酔うので、 深酒をしやすくなるのだそうです。 食べることで胃の粘膜に膜を作り、お酒がゆっくり吸収され、アルコールなどで胃が荒れてしまうのを防ぐ効果もあります。 お酒の後は水を2リットル飲むだけでも効果的! 飲む前に食事!と言われても、なかなか思うように進まず、ついつい飲みながら食べるとか、飲んでばっかりになってしまう。 そんな時に効果があるのが、飲んだ直後に水を2リットル摂取するという方法! 水を飲むことでアルコール代謝が促進されて、体からの排出が早くなります。 アルコールにはもともと「利尿作用」といって、おしっこを出させる効果もあるため、水はむしろ「たくさん飲まなければならない」と考えた方がいいみたいですね。 飲む前にウコン!で予防効果 どうにも断りきれなくて、いつもついつい深酒してしまう。 という人は、あらかじめサプリメントなどで予防をするのが一番効果が高くて確実です。 ホステスさんのように、毎日お酒を飲むことを仕事にしている人にも、サプリメントの愛用者が多いのだとか。 手に入りやすく効果がお手軽なのは、ずばりウコン!サプリメントのほかにも粉末タイプからドリンクタイプまで、ドラッグストアやコンビニなどで幅広く売られています。心配な時は一度使ってみてはいかがでしょうか?